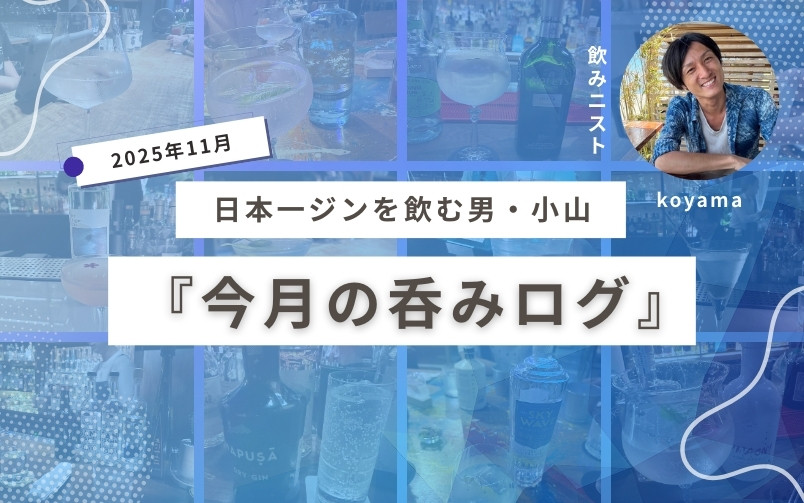GinYa MEDIAの徳留(@dome8686)です。 2025年9月7日、私はGinYa MEDIAのメンバーと共に、長野県の北部に位置する野沢温泉村を訪れた。この村の中心に佇む「野沢温泉蒸留所」の生まれるところを見に来るのが目的。
野沢温泉といえば、豊富な湯量と13の外湯めぐりで知られる日本屈指の名湯の地。しかし、近年、この村の魅力は温泉だけに留まらない。この地で生まれたクラフトジンが、国内外で高い評価を得ており、また、飲み慣れた方々だけでなくクラフトジン初心者の方々にも愛されている。
一杯のジンが生まれる背景にある、「水」や「コミュニティ」を体験する貴重な時間を体験することができたので、その体験を記事にした。
はじめに:旅のはじまりは、一杯の「NOZAWAギムレット」から

2025年9月7日、長く続いた夏の暑さがまだまだ続いていた9月。私たちGinYa MEDIAのチームは野沢温泉蒸留所に到着。スタッフの方々の温かい笑顔に迎えられ、差し出された一杯のウェルカムドリンク。それが野沢温泉蒸留所のクラフトジンを使用した「NOZAWAギムレット」
グラスの中で淡く輝く液体を一口含むと、まずライムの爽やかな酸味が駆け抜け、続いて驚くほど優しく、どこか懐かしい甘みが口の中に広がる。この甘みの正体は「かきどおし」という植物のお茶なのだとか。ジンのボタニカルな香りと地元の恵みが溶け合った、まさにこの場所でしか味わえない一杯。この土地の恵みがカクテルの中で見事に調和していて、これから始まる取材への期待が一気に高まる。

初日の夜は、村の中心にあるMusic Bar「GURUGURU」で、GinYaMEDIAのメンバーであるジェーニャさんがゲストバーテンダーを務めるイベントに参加した。カウンターの中でシェイカーを振るジェーニャさんと、それを楽しむ地元の人や観光客。言葉を交わし、笑い声が響く。ジンが人と人を繋ぐ、温かい時間がそこにはあった。そして私は外湯に浸かり、美味い寿司に舌鼓を打ち、初日から野沢温泉をすっかり満喫していた。
クラフトジンの水 ― 野沢温泉を巡る「水」

ジンやウイスキーといった蒸留酒にとって、「水」は味わいの根幹をなす最も重要な要素。野沢温泉蒸留所のクラフトジンがなぜこれほどまでにクリアで優しい味わいを持つのか。その答えは、野沢温泉村の壮大な自然が織りなす「水の循環」にある
ブナの森が紡ぐ、40年の旅
野沢温泉村は、広大なブナの原生林に抱かれている。冬、この森に降り積もった雪は、5月になるとゆっくりと解け始め、木々は青々とした新緑に包まれる。標高1400mの「上ノ平高原」に広がる豊かなブナ林は、その雪解け水や雨水をスポンジのようにたっぷりと保水するのだ。
大地に染み込んだ水は、実に40年から50年という長い年月をかけて地中を旅し、やがて里に湧き水や温泉となって姿を現す。この気の遠くなるような時間のフィルターが、野沢温泉の水を清らかで美味しいものに磨き上げ、私たちの生命、そして極上のジンを支えている。水の循環こそが、野沢温泉のすべての源なのだ。
命を潤す、豊かな水

取材2日目、私たちは蒸留所の代表取締役であるフィルさんの案内の元、実際にジン造りに使われている湧き水の場所を訪れた。こんこんと湧き出る水を手にすくって飲んでみると、その柔らかさに驚かされる。「とても柔らかく、クセが少ない。ごくごく飲めてしまう。」まさに、身体が喜ぶ水だった。
フィルさんは、「うちのジンの特徴もその水です。割り水する時には、この蒸留所から歩いて2分ぐらいの湧き水を使っていて。すごく柔らかい軟水なんです」と語ってくれた。
この驚きは、私たちが宿泊した宿「狸(たぬき)」でも続いた。部屋の水道の蛇口をひねると、驚くほど冷たくて美味しい水が出てくる。同行したメンバーが「なんかあの、浄水器が付いてるかのような冷たさと、あの美味しさ。あれは水道水じゃないですよね?」とフィルさんに尋ねると、「まあ、湧き水と水道水は、本当に同じようなものです」という答えが返ってきた。村の隅々にまで、豊かな水の恵みが行き渡っている。まさに「持って帰りたい」と心から思うほど、素晴らしい水だった。
この「豊かな水」があるからこそ、この土地ならではの温泉文化が花開き、この水があるからこそ、クリアで味わい深いジンが生まれる。そして、ジン造りに使われる杉やクロモジ、カキドオシといった植物もまた、この水で育っている。野沢温泉のすべては、この壮大な水の循環から始まっているのだと、深く納得させられた。
物語が生まれる場所 ― 野沢温泉蒸留所探訪

歴史を纏う空間と、巨大なポットスチルとの対面

蒸留所に足を踏み入れてまず驚くのは、和と洋が調合し洗練されたユニークな空間。この建物は、元々地元の野菜や山菜を加工する缶詰工場だったとのこと。約20年間空き家だった場所をリノベーションし、蒸留所として再生させたらしい。
「5年ぐらい前にオーナーから『この建物を使わないか?』という話があって。私達は長年持っていた、蒸留所を造りたいという夢がかなった」とフィルさんは語る。

バーカウンターとして使われている重厚な機械は、かつて野菜を蒸すために使われていたもの。歴史を尊重し、新たな価値を吹き込むその姿勢に、作り手の美学を感じる。
そして、空間の奥で圧倒的な存在感を放つのが、大きなポットスチル。 「みんな蒸留所に入ってくるとびっくりします。」というフィルさんの言葉通り、その大きさには思わず息をのむ。美しい銅の輝きを放つこの蒸留器から、野沢温泉の物語が詰まったジンが生まれているのだ。
野沢温泉のテロワールを映す、定番クラフトジン4種

野沢温泉蒸留所では、季節限定のものを除けば現在4種類の定番ジンが造られている。それぞれが持つ個性とストーリーを、フィルさんの解説と私の感想を交えてご紹介。
NOZAWA GIN
「野沢温泉の森を歩くときの香り」がコンセプト。杉やクロモジ、そして私がウェルカムドリンクで感動したカキドオシといったボタニカルが使われている。グラスに注ぐと、まるで雨上がりの森のような、湿った土と緑の香りが立ち上ります。口に含むと、クロモジ由来のハーバルでアーシーな風味が広がり、爽やかな余韻が長く続く。まさに、この土地のテロワールを象徴する一本。
CLASSIC DRY GIN
伝統的なドライジンの味わいをベースに、日本的なアクセントとして山椒を加えている。ビアフランカレモンの爽やかさと、ほのかに香るオリスルートのウッディで甘い香りが複雑に絡み合う。実は前日の夜、お寿司屋さんでこのジンのソーダ割りをいただいたのだが、ピリリとした山椒の刺激が魚の旨味と驚くほど合い、その美味しさに感動した。アルコール度数が47%と高めに設定されており、カクテルベースとしても抜群の存在感を発揮する。
IWAI GIN
爽やかなマイヤーレモンとジューシーなスモモのフルーティーさが特徴。フィルさんによれば、桜の葉・青紫蘇・りんごの木・すももが代表ボタニカルとのこと。「収穫の喜び→(祝い)」を表現したというこのジンは、野沢温泉の緑豊かな季節を思い起こさせる。トニックウォーターで割ると、その華やかな香りが一層引き立ち、心地よい甘みが広がる。
SHISO GIN
蒸留後に、商店街のカフェが作る特製の赤しそジュースを加えることで、ほんのりとしたピンク色と優しい甘みをまとわせたユニークなジン。アップルウッド由来のフルーティーさと、ハーバルな赤紫蘇の風味が絶妙にマッチしている。見た目の美しさもさることながら、味わいのバランスも見事。
土地と人が紡ぐ、特別な一本
定番商品に加え、野沢温泉蒸留所の真骨頂は、その土地ならではの文化や、バーテンダーとのコラボレーションから生まれる限定ジンもある。
例えば「DOSO GIN」は、日本三大火祭りの一つに数えられる野沢温泉で冬に開催される「道祖神祭り」で燃やしたブナの木を、蒸留器の中に入れて香りづけしたという驚きの一本。燻されたブナがもたらすバニラのような甘い香りは、祭りの熱気と神聖さを感じさせる。このジンは、単なる飲み物ではなく、村の伝統が宿った文化的なプロダクトと言える。
また、東京の有名Bar「Mixology Boutique」との共同開発で生まれた「ふきのとうジン」も印象的。雪解けと共に顔を出すふきのとうの独特な苦味を活かし、日本のビターズのような感覚で使えるジンに仕上げている。地域の素材を新しい形で表現し、トップバーテンダーと共に新たな価値を創造する。その姿勢は、クラフトジンの可能性を無限に広げているように感じた。
職人の魂 ― こだわりの製造工程と細部に宿る美学

こうしたジン造りを支えているのが、素材への徹底したこだわり。ボタニカルとして使うレモンは、瀬戸内産をフレッシュなまま年間4トンも仕入れ、スタッフが手作業と少しの機械で皮を剥いているという。
「その時期は蒸留所の中にはいいレモンの香りが?」とジェーニャさんが聞くと、フィルさんは笑顔で頷きました。4トンものレモンの皮を剥くという途方もない作業も、最高の製品を届けるための情熱があればこそ。蒸留チームは日々、新しいボタニカルを探求し、魅力的なブレンドを考え続けている。ちなみに皮を剥いたあとのジュースの部分はレモンチューハイやレモンジュースとして楽しんでいるそうだ。

細部にまで宿る美学は、ボトルデザインにも現れている。ロゴマークは、野沢温泉の水と季節の循環を表現したもの。よく見ると、円の中には野沢温泉の四季の風景や、カモシカの姿も描かれている。さらに驚いたのは、輸出用のボトル。なんと、底面にまでロゴがあしらわれている。一杯のジンに込められた、計り知れない情熱と美意識に、ただただ感服するばかり。
クラフトジンを味わい、村を知る ― 野沢温泉の文化とコミュニティ

野沢温泉を象徴する源泉の一つ麻釜(おがま)
野沢温泉のジンを深く理解するためには、そのジンを生んだ村の文化を知る必要がある。取材2日目の夜、私たちは幸運にも、この村の魂に触れる貴重な体験をすることができた。
湯けむりの向こうに ― 暮らしに根付く「外湯」文化

野沢温泉の暮らしの中心には、常に温泉がある。その歴史は古く、一説には聖武天皇の頃(724~748年)に僧「行基」が発見したとも言われている。江戸時代には飯山藩主によって湯治が許可され、多くの人々が訪れるようになった。
村内には「外湯(そとゆ)」と呼ばれる13の無料共同浴場があり、温泉街の散策と共に楽しむことができる。これらは観光施設ではなく、古くから「湯仲間」という制度によって地域住民が大切に維持管理してきた、生活に根差した場所だ。電気料や水道料を負担し、当番制で毎日掃除をする。そうやって、村の大切な財産を守り続けてきた。
実は私、温泉ソムリエでもある。
広報のかおるさんに勧められて訪れた「秋葉の湯(あきはのゆ)」は格別。アルカリ性の泉質はクレンジング効果が高く肌をさっぱりさせてくれる上に、化粧水成分でもあるメタケイ酸も含まれているため保湿効果も期待できる。質の高い源泉かけ流しのお湯に浸かりながら、この村が育んできた温泉文化の奥深さを感じた。また、熱いお湯で有名な野沢温泉の中でもぬる湯だという「熊の手洗い湯」にも足を運び、湯めぐりを満喫した。
魂が揺さぶられた夜 ― 野沢温泉秋祭り、神事のコミュニティ

取材日の9月8日は、偶然にも「野沢温泉秋祭り(湯澤神社例祭)」の開催日。これは、冬の道祖神火祭りと並ぶ、村を代表する大切な祭り。
燈籠行列や猿田彦の舞など、様々な伝統芸能が披露される中、私が最も心を奪われたのは「獅子舞」。2人1組で獅子を操り、お囃子に合わせて舞いながら、数時間かけて湯澤神社を目指す。
そこで繰り広げられていたのは、単なる舞踊ではない。獅子を操る二人とお囃子の演奏者たち。彼らの間には、言葉を超えたコミュニケーションが存在していた。視線や呼吸、漂う空気そのもので意思疎通を図る、まさに「あうんの呼吸」。それは、この日のために魂を込めて準備に勤しんできた者たちだけが共有できる、神聖な空間であった。

深夜、ようやく神社にたどり着き、最後の舞を終えた青年の、すべてを出し切ったような清々しい表情。それを見守っていた観客から送られる、温かい拍手。それは観光客向けのショーではなく、自分たちのコミュニティが大切にしてきたものを粛々と行う、本来の「祭り」、すなわち「神事」そのものの姿。
印象的だったのは、海外からこの村に移住してきた人々も、主体的に祭りに参加していたこと。彼らもまたコミュニティの一員として、村の伝統を共に担っている。外から来た者を受け入れ、共に新しいコミュニティを築いていく。野沢温泉という村の懐の深さと、人と人との強い絆を感じた、忘れられない夜となった。
人が繋がる、ジンが繋ぐ ― 野沢温泉での出会い

この旅で得たものは、ジンに関する知識や村の文化だけではない。それは、かけがえのない「人との繋がり」だ。
フィルさんと野沢温泉村

今回の取材で、蒸留所から村の隅々まで案内してくれたのが、スタッフのフィルさん。彼はオーストラリア出身。元々はスキーなどのウィンタースポーツが大好きで、1998年の長野オリンピック後に初めてこの村を訪れたそう。
「野沢温泉はスキー以上の魅力がいっぱいあって。この村が大好きになって。」
東京でサラリーマンをしながら、いつか野沢温泉に住みたいという夢を長年抱き続け、この蒸留所を立ち上げるプロジェクトをきっかけに、フルタイムでの移住を実現させたそうだ。彼の言葉の端々から、この村への深い愛情が伝わってきた。
ジンが紡ぐ夜

前述したMusic Bar「GURUGURU」でのゲストバーテンダーイベントは、まさにジンが人と人を繋ぐ瞬間だった。ジェーニャさんは、DOSO GINを使った「道祖マティーニ」やIWAI GINを使った「IWAIフィズ」など、この土地ならではのカクテルを創作。一杯のカクテルを介して、初めて会う人々の間に会話が生まれ、笑いの輪が広がっていく。その光景は、私たちGinYa MEDIAが目指す「楽しいGINライフ」そのものだ。

また、初日の夜にチームで訪れた寿司屋でのジンとのペアリングの話も書いておく。地元の新鮮なネタと、野沢温泉蒸留所のCLASSIC DRY GINで作ったジンソーダのペアリングは、まさに至福のひととき。「すごい美味しかったです」とフィルさんに伝えると、嬉しそうに頷いてくれた。野沢温泉のクラフトジンの持つ山椒の風味が、驚くほど寿司の味わいを引き立てる。その土地の酒を食事と共に味わうこと。これ以上の贅沢はないと、心から感じた。
さいごに:野沢温泉が教えてくれたこと
野沢温泉蒸留所のジンは、単なる美味しいお酒だけを意味しない。それは、この村の壮大な「水の循環」と、人々が幾世代にもわたって受け継いできた祭りや共同体という「文化の循環」、その二つの循環が溶け込んだ、液体のストーリーなのだと感じる。
ジンの一口に含まれているのは、ブナの森が育んだ清らかな水や、杉、クロモジといった植物の香りだけではない。そこには、温泉を守る人々の温かさや、祭りの夜に見た青年の情熱、コミュニティが一体となる空気感までもが、確かに溶け込んでいるのかもしれない。
ジンという一杯のグラスの中に、山や森、季節の移ろい、そして人々の暮らしが凝縮されている。このジンを飲むたびに、野沢温泉の美しい風景と、そこで出会った人々の笑顔を思い出し、またあの村を訪れたいなと感じるのだ。
この記事を読んでくださったあなたが、いつか野沢温泉を訪れ、ジンを片手にこの村の空気に触れてみたいと思っていただけたなら、書き手としてこれ以上の喜びはない。
関連リンク
野沢温泉蒸留所
- 公式サイト: https://nozawaonsendistillery.jp/
- Instagram:@nozawaonsendistillery
野沢温泉観光ガイド
- 公式サイト: https://nozawakanko.jp/



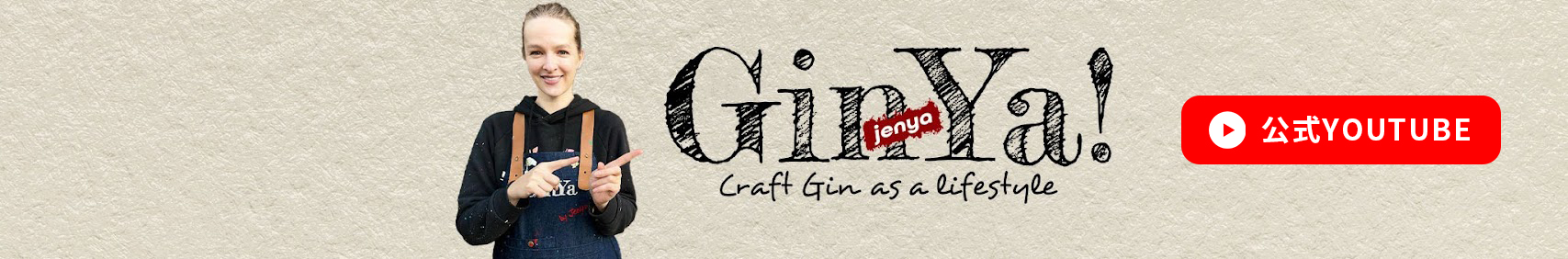

 ポストする
ポストする